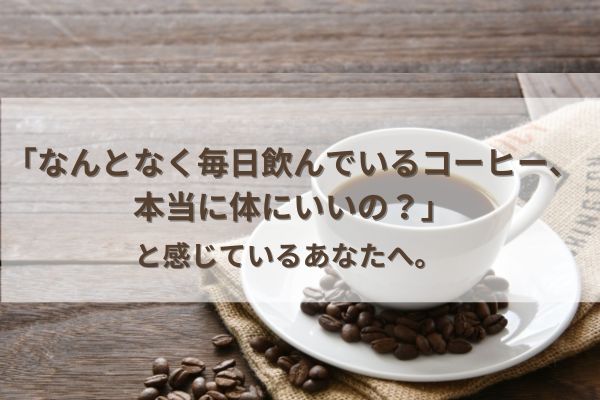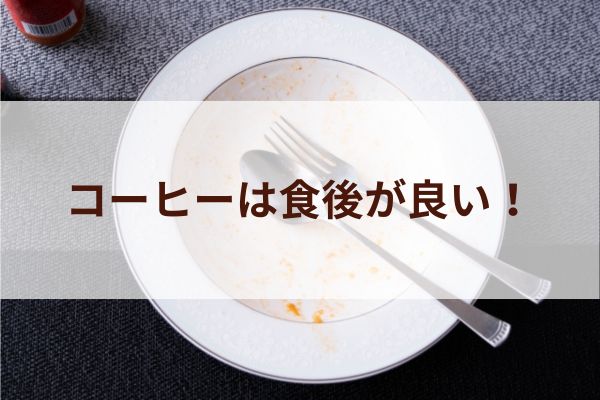コーヒーの効果と健康への影響
コーヒー 効果|効能 科学的に認められた主な健康効果とは?
抗酸化作用があり、健康維持や体の機能を守る効果が期待される
コーヒーには「クロロゲン酸」などのポリフェノールがたくさん含まれており、体のサビと言われる活性酸素を取り除く“抗酸化作用”があることがわかっています。
この抗酸化作用によって、細胞の老化を防ぎ、健康維持や体の機能を守る効果が期待されています。
血糖上昇リスクを低下させる
オランダのフリー大学アムステルダムの研究によると、コーヒーを日常的に飲む習慣がある人では、インスリンの効きが悪くなることによって血糖が上昇しやすくなる、代謝性の異常を発症するリスクが、最大で20〜30%低下することが報告されています。
肝臓機能を保護する
複数の研究結果を統合して分析する「メタアナリシス」の結果では、1日2〜3杯のコーヒーを飲む習慣は、肝臓の機能をサポートし、将来的な健康リスクを下げる可能性があることがわかっています。
Kennedy et al.(2016)、Alimentary Pharmacology & Therapeutics
認知機能の低下を抑え、脳の健康を守ることが期待できる
フィンランドで行われた長期追跡研究によると、中年期に1日3〜5杯のコーヒーを飲んでいた人は、高齢期になっても記憶力や思考力などの認知機能が保たれている傾向があることが分かりました。
このメカニズムとして、カフェインの神経保護作用や、抗酸化成分の脳内炎症抑制効果が考えられています。
CAIDE Study(Eskelinen et al., 2009)
一時的な注意力・集中力・覚醒の向上
Nehlig(2016)※1によると、カフェインは脳内にある「アデノシン受容体」と呼ばれる場所に結びつき、アデノシンという眠気を引き起こす物質の働きをブロックすることが分かりました。
これにより、脳の活動が抑制されにくくなり、中枢神経が活発化することで、眠気の軽減や、注意力・反応速度の向上といった効果が得られるとされています。
※1 Nehlig A., Brain Research Reviews, 2016
コーヒー 効果 |血圧への影響は上がる?下がる?

| 高血圧・カフェイン非耐性者 | カフェイン摂取30分以内に一時的に上昇する |
| コーヒーを毎日飲み、耐性が出来ている人 | 影響ほぼなし |
| コーヒーの習慣関係なく、カフェインレスコーヒー | 一時的な上昇なし |
一時的に血圧を上昇させる(特にカフェイン非耐性者)
カフェインは交感神経を刺激し、アドレナリンの分泌を促進するため、摂取30分以内に血圧を上昇させることが報告されています。
特にカフェインに慣れていない人や血圧が高めの人は、この影響を強く受けやすいです。上昇は通常3〜4時間以内に元に戻ります。
(Mesas AE et al., Am J Clin Nutr, 2011)
毎日飲む習慣がある人では、血圧への影響はほぼなくなる
コーヒーを飲む習慣のある人は、カフェインによる血圧の上昇に対する耐性が形成され、血圧が高めになるリスクが上がらないとされています。
デカフェコーヒーでは血圧への影響はほとんどない
デカフェ(カフェイン除去済みコーヒー)には血圧を上げるカフェインが含まれないため、一時的な血圧上昇作用は見られません。
むしろポリフェノール(クロロゲン酸など)による血管拡張作用や抗炎症効果がプラスに働く可能性もあることが分かっています。
循環器の健康をサポートする可能性がある
毎日3〜5杯ほどのコーヒーを飲む習慣がある人は、心臓や血管の不調のリスクが約15%減少すると報告されています。
この効果の背景には、ポリフェノールであるクロロゲン酸による抗酸化・抗炎症・血管保護作用が挙げられています。
American Journal of Agricultural and Food Chemistry(2017)
コーヒー 効果 |肌荒れや美肌への影響は?

抗酸化作用により、シミ・しわ・くすみなどの肌老化を抑える可能性がある
コーヒーには、「クロロゲン酸」や「メラノイジン」といったポリフェノールが多く含まれており、これらには体をサビつきから守る強い抗酸化作用があることがわかっています。紫外線やストレスによる活性酸素ダメージを抑制することが、肌のコラーゲン量の維持や色素沈着の抑止、弾力・透明感の保持をサポートすると報告しています。
Rodrigues et al.(2023, Cosmetics)
赤ら顔(ロザケア)の軽減効果がある
1日あたりコーヒーを4杯以上飲む人は、他の飲料を飲む人と比べて赤ら顔(ロザケア)の発症リスクが明らかに低いことが報告されました。この効果は、コーヒーの温度ではなく、カフェイン自体が血管を収縮させる作用に関係していると考えられています。血管の拡張による赤みを抑えることで、顔の赤らみが出にくくなるという仕組みです。
血流促進により、血色感とツヤ肌をサポートする
実際に、カフェインを摂取すると、皮膚の微小血管が刺激にしっかり反応し、血流がスムーズになるという研究結果も報告されています。
これにより、酸素や栄養が肌に行き渡りやすくなり、血色感やツヤのある健康的な肌の維持に役立つと考えられています。
Noguchi et al., 2015, J Pharmacol Sci
肌トラブルの原因になる可能性がある
カフェインを摂ることで、ストレスホルモンである“コルチゾール”が増加しやすくなることが臨床試験で確認されています。
このコルチゾールは皮脂腺を刺激し、皮脂の分泌を活発にするため、ニキビや肌トラブルの原因になる可能性があります。
コーヒー 効果|ダイエット 脂肪燃焼や代謝促進の仕組み
カフェインが脂肪分解(リポリシス)を促進する
Achesonら(1980年)の臨床試験では、カフェインを摂取すると血液中の脂肪酸濃度が上昇し、エネルギー代謝が高まり、脂肪の燃焼(=リポリシス)が促進されることが示されました。
これは、カフェインの作用で交感神経が刺激され、ノルアドレナリンやエピネフリンの分泌が増えることにより、β‑アドレナリン受容体が活性化されるためです。
その結果、ホルモン感受性リパーゼ(HSL)が働き、脂肪細胞から脂肪酸が血液中に放出される仕組みです。
脂肪酸は、運動や活動によってエネルギー源として利用されやすくなるため、運動前30〜60分前のコーヒー摂取が脂肪の燃焼に効果的とされます。
専門用語の解説
| ノルアドレナリン
(norepinephrine) |
ノルアドレナリンは、交感神経から分泌される神経伝達物質のひとつで、ストレスや緊張時に分泌が増加します。
血管を収縮させて血圧を上げたり、心拍数を上げたり、エネルギー代謝を促進するなど、「戦うか逃げるか」の反応(闘争・逃走反応)に関与します。 |
| エピネフリン
(epinephrine, 通称:アドレナリン) |
エピネフリンは副腎髄質から分泌されるホルモンで、ノルアドレナリンと似た働きを持ちます。
運動やストレス時に分泌され、心拍数の増加、血糖値の上昇、脂肪分解の促進などを引き起こします。脂肪燃焼の促進にも関わる重要な物質です。 |
| β‑アドレナリン受容体
(β-adrenergic receptor) |
これは、ノルアドレナリンやエピネフリンが作用する「受容体(センサー)」です。
体のさまざまな組織(心臓、脂肪細胞、筋肉など)に存在し、これが活性化されると:心臓では心拍が増える・脂肪細胞ではホルモン感受性リパーゼが働き、脂肪を分解(=リポリシス)といった生理反応が起こります。 |
| ホルモン感受性リパーゼ
(Hormone-Sensitive Lipase:HSL) |
脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪を分解して脂肪酸とグリセロールを取り出す酵素です。
脂肪燃焼(リポリシス)の“スイッチ”のような存在で、エネルギーが必要なときに活性化されます。 |
基礎代謝率を一時的に上昇させる
Dullooら(1989年)の研究では、カフェイン摂取によって安静時のエネルギー消費量(REE)が一回の摂取で約3~4%、一日を通じて最大11%まで増加し、この増加効果は摂取後約2.5時間続くことが示されました。
習慣的にカフェインを摂っている人でも、効果が完全に消えるわけではないとされています。
(Dulloo et al., American Journal of Clinical Nutrition, 1989)
クロロゲン酸が脂肪の蓄積を抑える可能性がある
コーヒーに含まれるポリフェノールの一種「クロロゲン酸」は、肝臓での脂肪合成を抑えるとともに、エネルギーとして使われる脂肪酸の燃焼が促進される作用が示されています。
このため、食後の血糖値とインスリンの上昇が緩やかになるとともに、内臓脂肪の蓄積を予防する効果も期待されています。
(Roles of Chlorogenic Acid on Regulating Glucose and Lipids, PMC 2013)
空腹時の摂取や飲みすぎは逆効果になることもある
空腹の状態で大量のカフェインを摂取すると、ストレスホルモン「コルチゾール」が過剰に分泌されやすくなります。
このホルモンが増えすぎると、脂肪分解を抑えるホルモンであるインスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことや内臓脂肪の蓄積につながるリスクがあると報告されています。
また、カフェラテやフラペチーノ、缶コーヒーなどに多く含まれる砂糖やミルクは、飲みすぎると余分なカロリーを取りすぎてしまう原因になります。
結果として、体脂肪の増加につながることも。そのため、「ブラックで、食後や運動前に飲む」がおすすめです。
コーヒー 効果|デメリット 飲み過ぎやカフェインの注意点
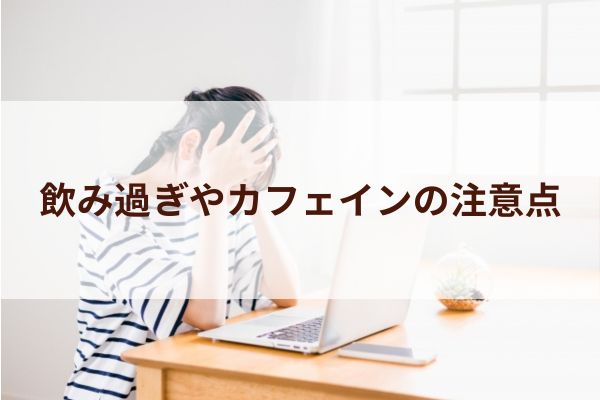
カフェインの過剰摂取は不眠・動悸・不安感を引き起こす
複数の研究によると、カフェイン摂取により睡眠潜時の延長、総睡眠時間の減少、睡眠効率の低下が確認されています。
また、カフェインには心拍数や血圧を上げる作用があり、とくに午後以降の摂取は不眠を招きやすいとされています。
一般的に1日あたり400mg(コーヒー約3~4杯)を上限とし、これを超えると心拍数の増加や睡眠障害などの副作用リスクが高まります。
Caffeine Effects on Sleep Taken 0, 3, or 6 Hours before Going to Bed,2013
胃酸分泌の促進により、胃もたれ・胃痛・胃炎を引き起こす可能性がある
コーヒー(特に空腹時の摂取)は胃酸分泌を刺激し、胃粘膜への刺激が強まり、胃痛や胸やけの悪化につながる可能性が示されています。
食後に飲んだり、ミルクやクリームを加えて飲んだりすることで、胃への刺激を和らげることができます。
Effects of Coffee on the Gastro‑Intestinal Tract: A Narrative Review(Nutrients, 2022)
鉄分やカルシウムなどのミネラル吸収を阻害する
コーヒーに含まれるポリフェノール類(特にクロロゲン酸やタンニン)は、食事に含まれる「非ヘム鉄(植物性食品に多い鉄)」と結びついて、吸収されにくい形に変えてしまうことが報告されています。そのため、鉄欠乏や貧血気味の人が食事中や食後すぐにコーヒーを飲むと、鉄の吸収が妨げられる可能性があると言われています。
また、コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があり、体内のカルシウムが尿として排出されやすくなることも知られています。こうした作用が続くと、長期的には骨密度の低下につながるリスクも指摘されています。
特に鉄やカルシウムが不足しがちな女性や高齢者、閉経後の方にとっては、コーヒーの飲み方やタイミングに少し注意を払うことが大切です。
Disler et al. (1975)“The effect of tea on iron absorption.”Gut, 16(3), 193–200.
Heaney RP et al. (1982)“Effects of caffeine on bone and the calcium economy.”
頭痛・離脱症状を引き起こすことがある
カフェイン依存が形成されると、コーヒーの飲用を急にやめた際に、頭痛・疲労感・集中力低下などの離脱症状が現れることが知られています。
毎日3杯以上飲んでいる人が突然やめると、2〜3日以内に頭痛やイライラが出やすいため、減量は徐々に行うのが理想です。
(Juliano LM, Griffiths RR., Psychopharmacology, 2004)
効果を高めるコーヒーの飲み方
効果が出るまでの時間と持続時間は?
カフェインの効果は摂取後30〜60分で最大になる
カフェインは小腸から素早く吸収され、摂取30〜60分後に最も高い覚醒・集中力向上効果が得られると研究で示されています。
特に、朝食後や昼食後の摂取タイミングは、このピーク効果と重なるため、仕事や勉強への集中力を最大限に引き出すタイミングとして推奨されています。
(Lorist & Snel, 2008; Van Soeren et al., 2004)
覚醒・集中力の効果は約3〜6時間持続する
カフェインは健康な成人では体内で半分に分解されるまで(血中半減期)に約4~6時間かかり、これに伴う覚醒作用や集中力向上も摂取後約3〜6時間続くとされています。そのため、夕方以降にコーヒーを飲むと、就寝に影響を与える可能性が高くなるため注意が必要です。
A review of caffeine’s effects on cognitive, physical and occupational performance
脂肪燃焼・代謝促進の効果は摂取後約1時間から始まり、3〜4時間続く
カフェイン摂取後、アドレナリン分泌が増加し、脂肪分解(リポリシス)や基礎代謝の上昇が1時間以内に始まり、約3〜4時間持続すると報告されています。
運動の30〜60分前に飲むことで、脂肪燃焼効率を高められる可能性があります。
Metabolic effects of caffeine in humans: lipid oxidation or futile cycling?
利尿作用や胃腸への影響も摂取後1時間以内に現れる
Neuhauser‑Bertholdら(1997)の研究では、コーヒーを飲む人は飲用後に尿量が増える傾向があり、これは利尿作用に起因する可能性があります。
一方、Cohen & Booth(1975)はカフェインが胃酸分泌を促進し、胃や腸の活動を活発にすることを報告しています。
会議や長時間の移動の前にコーヒーを飲む場合、これらの影響を踏まえてタイミングを調整するのが望ましいとされています。
Gastric acid secretion and lower-esophageal-sphincter pressure in response to coffee and caffeine
コーヒー 効果 |空腹時・食後どちらが良い?
食後に飲むことで胃への負担が少なく、安定した効果が得られる
すでに記述しましたが、空腹時に飲むコーヒーは胃酸分泌を強め、胃の不調を招きやすいとされています。
一方で、食後にコーヒーを飲む場合は、胃の中に食べ物が存在するため、コーヒーによる胃酸分泌の刺激が緩やかになりやすいとされます。
食物が胃粘膜の保護クッションとなることで、胃への直接的な刺激を軽減する働きがあるからです。
このため、胃が弱い人や胃もたれ・胸やけを感じやすい人にとっては、空腹時よりも食後のコーヒー摂取のほうが比較的安全とされています。
Effects of Coffee on the Gastro-Intestinal Tract: A Narrative Review and Literature Update
食後のコーヒーは食後血糖値の上昇を緩やかにする可能性がある
コーヒーに含まれるポリフェノールの一種「クロロゲン酸」には、肝臓での糖新生(体内でブドウ糖を新たに作り出す働き)を抑える作用や、腸での糖吸収のスピードをゆるやかにする効果があるとされています。
そのため、食後にクロロゲン酸を多く含むブラックコーヒーを飲むことで、急激な血糖値の上昇(血糖値スパイク)を防ぐ可能性が示唆されています。
実際に、Johnstonら(2003)の研究では、コーヒーの摂取によりGIP(消化管から分泌され、インスリンの働きを促すホルモン)の分泌が抑えられ、GLP-1(血糖値の上昇をゆるやかにし、満腹感にも関与するホルモン)の分泌が増加することが確認されました。
これにより、腸での糖の吸収が遅れ、血糖値の上昇が穏やかになります。
また、Olthofら(2009)は、クロロゲン酸を含むコーヒーを飲んだグループでは、食後30分の血糖値が低くなったことを報告しており、血糖変動を和らげる作用があることを裏づけています。
Johnston et al. (2003), American Journal of Clinical Nutrition
Olthof et al. (2009), Diabetes Care
空腹時の摂取は胃を刺激しやすく、体質によっては避けたほうがよい
すでに記述しましたが、空腹時に飲むコーヒーは胃酸分泌を強め、胃の不調を招きやすいとされています。
朝起きてすぐにコーヒーを飲む習慣のある人は、水や食事を先に摂ってからコーヒーを飲むことで不調を回避しやすくなります。
ダイエットや脂肪燃焼目的の場合は「軽食後+運動前」が最適
ダイエットや脂肪燃焼を目的とする場合、「軽く食事をしてから運動する前」にカフェインを摂取することで、脂肪が効率よく燃焼されるという研究報告があります。
たとえば、あるメタアナリシス(複数の信頼性の高い研究結果を統合して分析した総合研究)では、軽食後5時間以内に、カフェインを摂取した場合、運動中に脂肪酸の酸化(脂肪が分解されてエネルギーとして使われること)が有意に増加するという結果が示されています。
コーヒー 効果 |インスタントでも効果が期待できる
インスタントコーヒーにもカフェインが含まれており、覚醒・集中力向上効果は基本的に同じ
インスタントコーヒー1杯に含まれるカフェインは、ドリップコーヒーに比べてやや少ないものの、多くの研究で『少量でも眠気覚まし・注意力向上・パフォーマンス維持に十分効果がある』と報告されています。
食品成分データベースによると、インスタントコーヒー(顆粒製品)100gに含まれるカフェインは4gと記載されています。
Effects of Caffeine on Cognitive Performance, Mood, and Alertness in Sleep-Deprived Humans
食品成分データベース:し好飲料類/<コーヒー・ココア類>/コーヒー/インスタントコーヒー
インスタントにも抗酸化成分(クロロゲン酸など)が含まれており、美肌・抗糖化などの効果も期待できる
Budrynら(2009)の分析では、インスタントコーヒー加工時にもクロロゲン酸など抗酸化ポリフェノールが保持されており、その抗酸化力が製品に残ることが示されています。
また、別の研究では、クロロゲン酸が紫外線による皮膚の酸化ダメージや色素沈着を抑える可能性が報告され、インスタントコーヒーにも美肌・抗糖化などの効果が期待できることが裏付けられています。
Development of an instant coffee enriched with chlorogenic acids
カフェイン量・ポリフェノール量は製品によってばらつきがある
製品ごとに使用する豆の種類・製法・濃度が異なるため、同じインスタントでもカフェイン量や抗酸化成分に差があると報告されています。
効果を求めるなら、無糖・無添加のピュアタイプを選び、濃さを濃い目に調整することが推奨されます。
(Crozier et al., Food and Function, 2012)
まとめ
この記事を通じて、コーヒーが健康・美容・代謝といった幅広い面で、科学的な根拠に基づいた効果をもたらすことがお分かりいただけたかと思います。
覚醒作用や血糖コントロール、美肌やダイエットのサポートなど、目的に応じて適切に取り入れることで、コーヒーはより良い毎日の味方になります。
ご自身の体調やライフスタイルに合わせて、適量や飲むタイミングを意識することも大切です。
そうすることで、コーヒーは単なる嗜好品を超え、日々の健康づくりをそっと支えてくれる存在となるでしょう。