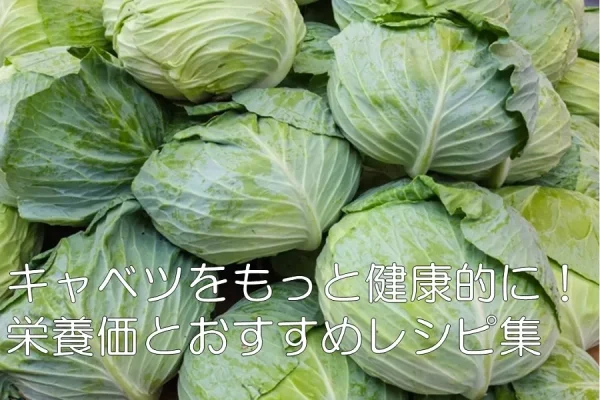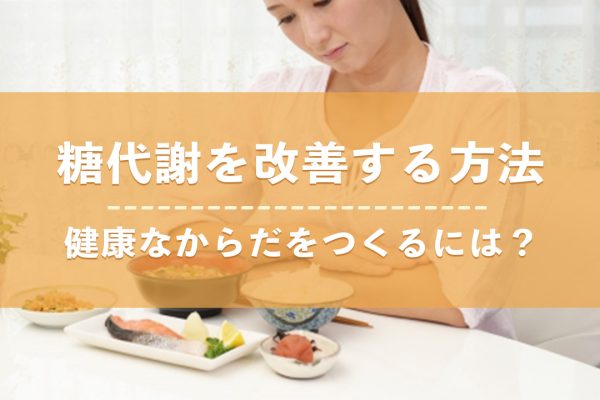
INFORMATION暮らしのお役立ち情報
健康な暮らしを応援する
最新トピックス

PICK UP NEWS
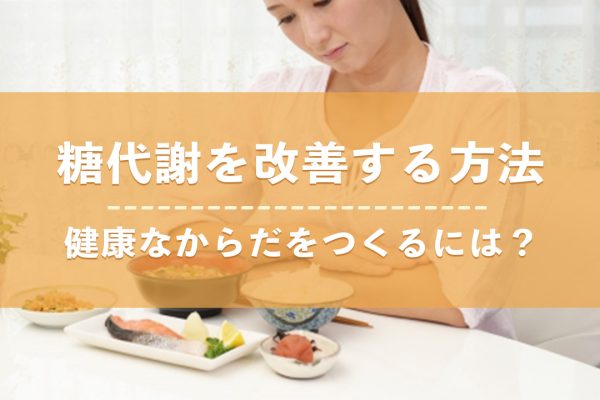

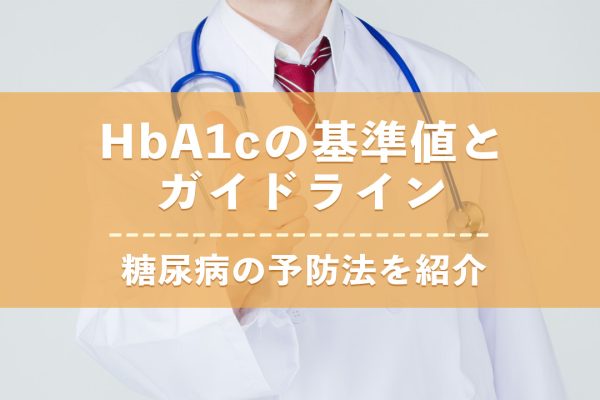
食事制限

糖質制限中に食べていいもの|シーン別・具体例つき完全ガイド
2025.7.7
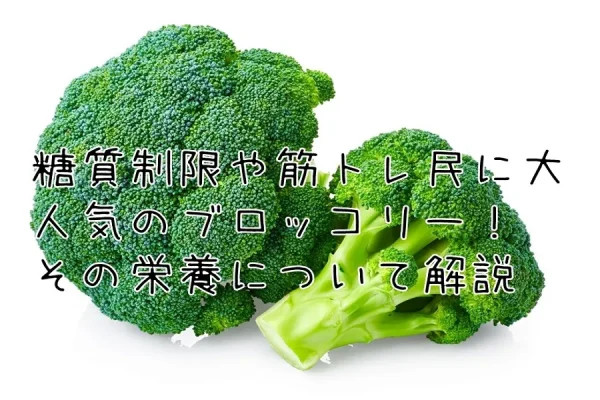
糖質制限や筋トレ民に大人気のブロッコリー!その栄養について解説
2025.7.5

レタスの栄養と驚くべき健康効果とは?
2025.7.5
からだの不調

糖質疲労とは|血糖値の乱高下による体の不調が関係している可能性も
2025.6.11
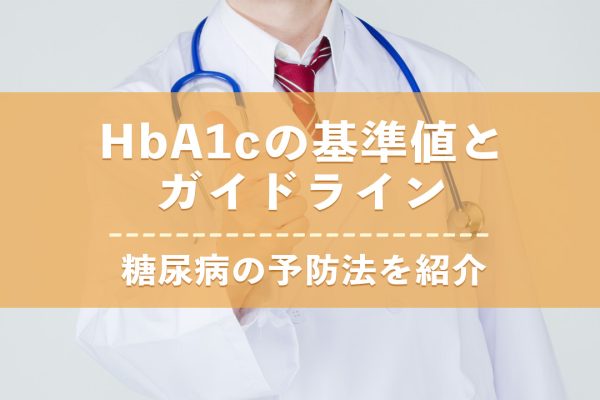
HbA1cの基準値とガイドラインを理解して糖尿病の予防を目指す方法
2025.6.11
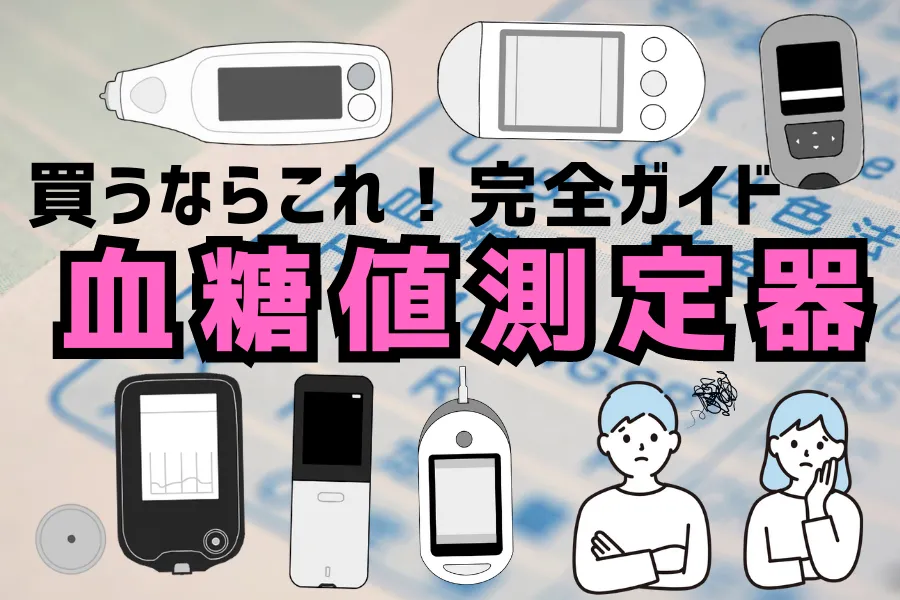
血糖値測定器を買うとしたらこれ!血糖値測定器完全ガイド
2023.8.11
ダイエット
ウワサの真相Q&A